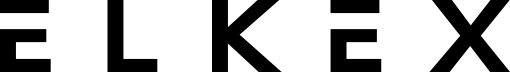ジャズシーンを牽引したハードバップの特徴
2023.09.04ジャズシーンを牽引したハードバップの特徴

モダンジャズの中で最もモダンジャズらしいハードバップ。ジャズを全く知らない人がハードバップの曲を聴いてもジャズらしさを感じるのがハードバップの特徴です。
いわゆるジャズらしいこの演奏スタイルは、カフェやレストランなどで耳にしている方も多いはず。
今回は現代でも触れる機会の多いハードバップについて解説していきます。
1 ハードバップとは
ハードバップは、1950年代半ば頃から1960年代にかけてニューヨークを中心に盛り上がったジャズ・スタイルのことを指します。
1940年代に生まれたジャズのスタイルであるビバップをベースにしながらも、より大衆性や芸術性が加えられたスタイルの音楽となっています。
ビバップでは、コード進行に沿いながらやや難解なフレーズのアドリブが展開されていますが、ハードバップでは基本的な手法に大きな違いはないものの、フレーズがより洗練されたことでメロディアスで聴きやすい曲が多いのが特徴です。
2 ハードバップの成立ち
ジャズの初期全盛期がスイングジャズの頃だとすると、ハードバップはジャズが最も栄えた全盛期と言えます。
現代にも続くジャズのスタンダードナンバーと言われる曲の多くはハードバップの曲でもあります。
ビッグバンドによるメロディー、アンサンブル重視の曲が多いスウィングジャズで大いに盛り上がったジャズですが、その後スウィングジャズにマンネリ化を感じ、もっと個人のアドリブを中心とした演奏形式をとりたいとビバップが流行します。
コンボ形式による個人のアドリブ重視、即興演奏、刺激的な曲の多いビバップがマンネリ化を迎えると、今度はもっと聴きやすく洗練された演奏を中心としたクールジャズ、ウェストコーストジャズが誕生。
そしてその次に生まれたスタイルが、ハードバップというスタイルです。
このハードバップは、1950年代半ばから1960年代半ばまで流行し、いわゆるジャズの黄金時代の象徴となりました。
3 即興演奏の流れをより重要視するように
個々のテクニックよりも楽器編成やアンサンブルを重視したクールジャズや、教会旋律のモードや数少ない音階だけで作品を作るモードジャズなど、モダンジャズは様々な音楽スタイルによってシーンを牽引してきました。
そのためハードバップ以前のジャズは即興演奏の重要性が決して高くありませんでした。
対してハードバップは熱狂的な即興演奏を特徴としていました。
すなわちアドリブ性が強く、メロディーラインを活用した演奏も多かったため、これまでのモード奏法への脱却を試みられるようになります。
4 ジャズ史に残る錚々たるメンバーが演奏を行ったハードバップ
この時代のアーティストの一例としては、
- マイルス・デイヴィス
- ジョン・コルトレーン
- ソニー・ロリンズ
- ホレス・シルバー
- アート・ブレイキー
- クリフォード・ブラウン
- セロ二アス・モンク
- ミルト・ジャクソン
など、名前を挙げればきりがありません。
ハードバップ幕開けの号砲を放ったのは1951年録音のマイルス・デイビス「ディグ」だという説も有力です。
この「ディグ」にはテナーサックスのソニー・ロリンズ、アルトサックスのジャッキー・マクリーン、そしてドラムのアート・ブレイキーといった錚々たるメンバーが参加し、若々しさは残るものの新時代の到来をうかがわせる演奏を見せてくれます。ビ・バップからクール、さらにはハードバップと、ジャズの変遷を牽引したマイルスの功績は非常に大きいでしょう。
さらに1954年、ニューヨークのライブハウス「バードランド」で録音された「バードランドの夜」は「ハードバップ誕生の瞬間」を捉えた歴史的名盤といわれています。
演奏するのは「ジャズ・メッセンジャーズ」の前身となるアート・ブレイキーとピアノのホレス・シルヴァーによる双頭クインテット。
後にドラマーのマックス・ローチとのクインテットを立ち上げるトランペットのクリフォード・ブラウンなど、数々の大物がセッションに参加していたことを考えても「バードランドの夜」の価値の高さが分かります。
死ぬまでジャズの最前線に立ち続け、常に時代の一歩先を行ったマイルスは中心としながら、ジョン・コルトレーンやソニー・ロリンズといったマイルスの門下生、その後30年以上にわたり、若手の登竜門「ジャズ・メッセンジャーズ」のリーダーとしてジャズ界を牽引するアート・ブレイキーとその師弟達など、数多くのミュージシャンがシーンを盛り上げます。彼ら先駆者のほとばしる音楽への情熱がこの後1960年代にかけて絶頂期を迎えるジャズ黄金時代の礎を作り上げていきます。
現代でも色褪せないハードバップをぜひ楽しんで
70年以上も前に勃興したハードバップは、現代でも触れる機会が多いいわゆるジャズらしい音楽です。
BGM的に耳にしていることも多いこのスタイルですが、アーティストごとの特徴や背景、楽曲の多種多様さなど非常に奥深い楽しみ方ができる一面も。これを機にぜひハードバップジャズの世界を楽しんでみてください。